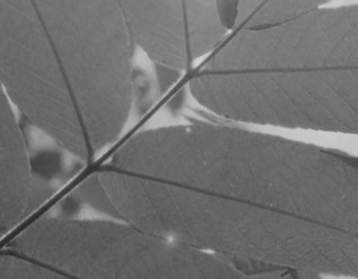
澄んだ青空に原は目を向けた。
骨休めは無理でも、たしかにこのト島で寝起きすれば良い気分転換になるだろう。
白い雲の峰が眩しく輝く。
鳥が囀りながら空を高く舞う。
朝の爽やかな風が原を追い越して駆け抜けていく。
原は気持ちがいつになく高揚するのを覚えた。
自然と歩調が速くなる。
どこまでも歩いて行きたかった、できることならあの青空にそびえる岩山の頂まで……。
だが、日差しがだんだんと強くなるにつれ、誰にも告げず宿舎を抜け出してきたことが気にかかった。
そろそろ朝食の時間かもしれない。
原は名残惜しそうに野山を一瞥すると、くるりと向きを変え宿舎のほうへと戻りだした。
放牧地を過ぎ、敷地内の林をぬけ、自分の部屋の窓を目指していた原の鼻先に、コーヒーのいい香りが流れてきた。
窓がひとつ大きく開かれており、中途半端な開き方をした深紅のカーテンが風に揺れている。
……長官の部屋だ。
窓を見上げた原の目に、不意に大石の姿が映った。
大石も原に気がついたらしく、片手を上げて彼に合図を送った。
「おはよう、朝の散歩かね? こっちに上がってきたまえ!」
艦から運ばせたのだろう、大石はコーヒー道具一式を部屋に持ち込んでいた。
コーヒーを人にふるまう時の大石はとても楽しそうである。
いそいそとカップを温め、淹れたてのコーヒーを注意深くカップに注ぐ大石の表情は、まるで玩具に夢中な子供のようだ。
コーヒーを淹れる大石を間近に見るのは今朝が初めてではないが、原はひどく戸惑いを覚えた。
無邪気で楽しげな大石の表情……これがこの人の素顔なのだろうか?
あの鬼謀の将がこんな子供のような顔をするなんて、可愛らしいというか、意外というか……。
原の大石観はまたもや混乱してしまうのだ。
「休日の朝のコーヒーはまた格別だな」
カップを手にした大石が笑いかけてきた。
「どうした? ぼんやりして」
大石の声に原ははっと我に返った。
「いえ、こんなに気持のいい朝は久しぶりで……」
とっさに返した原の言葉に、思いもかけず、大石は深い理解をこめてしみじみと頷いてみせた。
「うむ、君にはまったく苦労をかけたからな」
心に沁みる深い響きを持つ声に、原は覚えず胸が熱くなった。
……ああ、長官は俺の苦労をわかってらしたんだな……。
他愛ないとはわかっているが、大石に真顔でこんな言葉をかけられると、心に甘い霧がかかってしまう。
原は感動を隠すように目を伏せると熱いコーヒーを一口啜った。
ほどなく、従兵長が顔を出して食事の用意ができたことを告げた。
「なんでしたら、こちらにお運びしましょうか」
「そうだな、そうしてくれるか」
万事気のつく従兵長に、大石が無造作に頷いてみせる。
すぐに銀のトレイに乗せられて、湯気を立てた朝食が運び込まれてきた。
日本武尊の割烹手ではなく、現地のコックが調理したものらしく、いつもとメニューが違って目新しい。
熱い脂の垂れているベーコンにフライドエッグ。
みずみずしいサラダにくし切りにされた香り高いオレンジ。
地上ならではの新鮮な食材に、原は思わず笑顔になった。
大石も真剣な顔つきで、焼きたてのトーストにべったりとマーマレードを塗りつけている。
……あれ? 長官は甘党ではなかったと思ったんだが?
「英国風マーマレードは濃厚で旨いぞ……堅めだからよく乗るな、ほらどうだ」
大石がにっこり笑って差し出して見せたトーストに原は絶句した。
薄いカリカリのトーストの上に、同じぐらいの厚さのマーマレードが塗りつけられているのである。
「さっ食べたまえ!」
「えっ私が食べるんですか、これ」
「そうだ、君のために作ったんじゃないか」
「は、はぁ……ありがとうございます」
あの大食らいの航空参謀なら喜んで食べるだろうが、と原はトーストを受け取りながらげんなりした。
……私はあまり甘いものは好きじゃないんですよ……出撃以来、ずっと一緒に食事してきたのになぁ。やっぱり長官は俺のことをあまりわかってられないような。
マーマレードのせいでどっしりと重いトーストを、原はしぶしぶかじりだした。
甘い。
半端でなく甘い。
オレンジ色のようかんをパンの上に載せたようなかんじだ。
おまけに山盛りのマーマレードをこぼさないようにするには、なかなか苦労がいり、行儀のいい原を困惑させた。
「この黒いスプレッドはなんだろうな? 原くん、試してみるか?」
大石はいい気なもので、珍しげに違うビンに手を出している。
「いえ、パンはもう結構です」
顔をしかめて原が即座に断る。
「そうか? 小食だな。お互い兵学校のころは毎朝半斤のパンでも足りなかったのになぁ、ははは」
愉快そうに笑う大石の顔にちらっと冷やかな視線を走らせると、原はナプキンの端で口元を品よく拭った。
……ええ、今はお互い四十の坂を越しているんですからね。二十歳前のような食欲があるわけないでしょう!
好奇心旺盛な大石は自分のトーストに黒いスプレッドをべったりと塗りつけている。
原はあえて黙ってそれを見ていた。
フランス駐在員の経験のある彼は、その黒いスプレッドがなんであるか知っていた。
そしてその強烈な味も……。
「不味い! なんだこれは!」
マーマイト(イーストを発酵させた塩辛いペースト)を口にした大石の、英国人以外が十人中九人までが見せる反応を、原はすましてみつめていた。
「お口に合いませんか」
「合わん!」
「西洋の味噌ですよ、いわば」
「知ってたのなら言ってくれればいいのに……原くんも意地が悪いな……」
塩辛さが堪えたのだろう、大石は鼻声になっている。
テーブルの向かいでは彼の参謀長が涼しい顔で紅茶ポットに手を伸ばしていた。
「紅茶をお注ぎしましょうか?」
「……うん」
「ミルクは?」
「いや、いい」
注いでもらった紅茶を、まだ渋い表情で大石は口元に運ぶ。
原は素知らぬ顔でベーコンを切り分けている。
マーマレードの仕返しのつもりだ。
会話が途切れ、食器の触れあうかすかな物音だけが聞こえていた。
食卓に飾られた一輪ざしの花が、黙ったままのふたりを静かに見守っていた。
紅茶を飲みほした大石がようやく口を開いた。
「……美味い紅茶だな」
「セイロンティーだそうです」
「ふうん、旭日艦隊にも少し都合してもらおうか」
「手配しておきます」
「うん……」
天井ではシーリングファンが物憂げに回り、ゆっくりと部屋の空気を動かしていた。
秀麗な面持ちの参謀長は、大石に構わず黙々と食事を続けている。
沈黙に耐えかねた大石が機嫌を取るように再び話しかけた。
「……その、いいもんだな、こういうふたりきりの朝食も」
「そうですね」
「なんとなく落ち着く」
「ええ」
言葉少なに原が答えた。
テーブルの向かいでは大石がちょっとばつの悪そうな顔になっていた。
原は相変わらず澄ました表情でナイフとフォークを動かしている。
傍若無人で魅力たっぷりな長官と付き合っていくコツが、少し飲みこめたような気がする。
……これからは負けてばかりいませんからね、長官。
朝の散歩のせいか今朝の原はなんとなくそんなポジティブな気分だったのである。