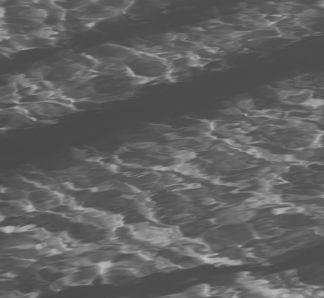
「……というわけで、日本武尊から水泳達者を推薦していただけませんか」
折入って相談が、と原に真剣な顔つきで声をかけられて、いったい何事かと構えていた艦長は、話を聞き終えてほっと安堵の息をついた。
「米軍の温水プールで……長官らしいですな」
言外にかすかな非難を滲ませながらも、富森はほろ苦くほほえんでみせた。
「参謀長もお忙しいでしょうに……」
長官のお守りも大変ですな、という部分は飲み込んだまま、彼は言葉を続ける。
「そうですなぁ、アメリカに負けない水泳達者となると……」
兵学校でも水泳訓練はたっぷりやるが、軍の水訓はスピードより持久力を重視するので遠泳が中心になる。
競泳もやることはやるが遠泳ほどではない。
「水泳部や水球部だった予備学生出身者を探してみましょう。下士官兵にも適任者がいるかもしれません……うぅむ、いっそ旭日艦隊から広く選抜しては?」
やはり前世からの転生組は潜在的に米軍に対抗意識が強いのだろうか――日ごろ穏やかな富森がいつになく意気込んでいた。
原から相談を受けてすぐ、富森は日本武尊から護衛の駆逐隊、遊撃艦隊や潜水戦隊にまで手広く声をかけて調べてくれたようだ。
早くもその日の夕方、夕食のため食堂に向かう原を呼び止めると
「参謀長、すごい逸材がいましたよ。四百メートル自由形世界記録保持者です」
そう口早にささやきかけたのである。
「ええっ! 世界記録!」
「当艦乗組ではありませんが、《熊野》の軍医長、M少佐です。彼が学生時代に出した世界記録はまだ破られていないということです」
「すごい……!」
「まったく多士済々ですな、旭日艦隊は。とりあえず六人選んでみました。ご覧ください」
思いがけない戦果に驚く原に富森はリストを手渡した。
富森がリストアップしたのは世界記録保持者のM軍医のほかに、予備学生出身のS大尉、О大尉――このふたりは戦争がなければ五輪候補になっただろうという実力者だ。
いずれもプールの話を持ちかけたら、米軍に日本水泳の実力を見せつけてやります! と、大乗り気になったという。
下士官兵からは、兵学校の水泳担当教員だったB兵曹、同じく機関学校水泳担当教員C兵曹、中学全国大会で準優勝したC上水。
富森の言葉通り、旭日艦隊は多士済々の大所帯、探せばみつかるものである。
問題は艦も配置もバラバラな六人を、いかに支障のないよう借り受けるかだった。
まずM軍医の《熊野》は明日からスコットランド沖での護衛任務が入っている。
まさか軍医長なしで出航させるわけにいかないので相応の処置が必要だ。
「代わりの軍医を用意しなくてはならん……こんなことは褒められたことではないが」
原が苦い顔でつぶやく。
またC兵曹の《ア号潜》は現在イーサ周辺を警戒潜航中だ。
「うーん、一度浮上してもらうか……逸脱行為も甚だしいが」
やや忸怩たる様子の原の背を押すように
「たまにはこういうこともありかと……日本武尊の乗員については私が手配しておきますのでご安心を」
富森がそう控え目に励ました。
たしかに軍律上好ましくないが、それもこれも日本海軍の面子のためである。
なにより米軍にひと泡吹かせられると思うと、ふたりの顔には大人げない薄笑いさえ浮かんでくる。
「……まさか、五輪レベルの水泳選手がこっちにいるとは思わないでしょうな」
「……なかなか痛快ですな」
原と富森はにやりと笑い交わすのだった。
大石には自分の水泳のために、原たちがあれこれ腐心していたなど思いも寄らないことだった。
ただ原が随員だとつけてくれた士官たちが、見たことのない顔ばかりなのを妙に思っただけである。
「なにっ! 世界記録に五輪候補?!」
原から紹介されて大石は目を剥いた。
「どこから連れてきた?! え、うちにいた?! うーん、やることが徹底してるな、原くんは……」
驚き喜びながらも大石は自分から右手を差し出して
「とにかく光栄だ。よろしく頼むよ」
と五輪級選手である士官三名とそれぞれがっちり握手を交わした。
「おお、君たちも頼もしいな。よろしくな」
下士官兵三名の緊張した敬礼にも、彼は闊達な笑顔でうなずき返した。
選抜された随員六名は、いずれも胸板が著しく発達した水泳体型……。
余裕のあるはずの機内がどうも狭苦しかった。
原が危惧したとおり、ケプラビーク基地のプールサイドは見物客でいっぱいだった。
ハダカの旭日艦隊司令長官を一目見ようと、物見高い米軍の将校・下士官兵で人だかりができている。
プールだけでなく、隣接した建物の窓にも双眼鏡を手にした野次馬が鈴なりになっていた。
ほら、いわんこっちゃない! これじゃあ見せ物です!
原がいれば、そう舌打ちして憤慨しただろう。
プールサイドに旭日艦隊の一行が現れると、それら多数の観衆が一斉にどよめいた。
――オオゥ!
露出度の高いジャパニーズスタイルの水着に観衆の視線が集中する。
旭日一行は長官を守るように若い随員たちが大石を取り巻いていた。
いずれもきりっと引き締まった逞しい身体をしており、十分鑑賞に堪えうる裸体だ。
大石自身も普段から体力保持を心がけているだけあって、脱いでも決して見苦しい身体ではない。
広い肩、厚い胸板、六尺近い長身、むしろ立派な体格だ。
彼は平然と視線を受け止め、堂々とした態度で水際に近寄った。
米軍はプールの四分の一を旭日一行のために空けてくれていた。
「メニューは君に任せるよ」
「はい、承知しました。ではまずウォーミングアップから。各自得意な泳法で軽く往復してきて下さい」
M軍医に指示されて、一行は水に入り順番に泳ぎだした。
磯貝もそこそこ達者な平泳ぎで水面をスイスイとよぎっている。
「ほほう、みなたいしたもんだ」
「では長官、まいりましょうか」
最後に残った大石もM軍医に促されてプールの底を蹴った。
大石のストロークに合わせて、M軍医もゆっくりと進む。
日本側が借り切ったコースから元気な水しぶきが上がっていた。
くるりと切られるターン。
すうっと水面下で進む人影。
選り抜きの水泳達者たちに交じって大石も負けずに水面を割って進む。
……ああ、綺麗に泳がれるじゃないか、よかった。
旭日艦隊の水泳達者たちは、大石の泳ぎに胸をなでおろしていた。
彼は長い手足を活かして、さほど速くはないがゆったりと優雅に泳ぐ。
肝心の大石がバシャバシャモタモタしていたら格好がつかないところだった。
日米対抗リレーは原の杞憂に終わった。
オリンピック級選手の登場にすっかり戦意喪失したのか、アメリカ側から対抗リレーの申し出はなかったのである。
ウォーミングアップの後のM軍医・S大尉・О大尉のフルスピードの模範演技で、アメリカ人たちはすっかり度肝を抜かれてしまったのだ。
その力強い華麗な泳ぎは桁外れに速く、まるで旧式艦艇を追い抜くミサイル艇といった景色である。
中央を世界レベルのこの三名にあてがって、そちらで彼らにガンガン泳がせて米軍へのデモンストレーションとし、残りのスペースで大石と随員たちがまったりと遊泳――
その日の午後いっぱい、大石たちは久しぶりのプールを存分に楽しんだ。
大石たちは遊泳の後、将校ホールで勧められるままに酒を飲んだ。
たっぷり泳いだ後のけだるい身体にスコッチがじんわりと温かくしみわたる。
五感はどこかぼんやり鈍く、気分だけがやけに高揚している。
いつになく、酔っている。
大石にも酔いの自覚はあった。
バーの奥に、黒光りしたグランドピアノが照明を受けて鈍く浮かび上がっているのが目に付いた。
彼はふらりと立ち上がり、ピアノに歩み寄ると演奏用のベンチに無造作に腰掛けた。
いきなり、大石の両手が鍵盤の上で軽やかに動きだす。
唐突に確かな旋律が流れでて、室内の人がみなハッとして顔を上げた。
半目を閉じた表情で大石は手元だけをみつめている。
甘いスタンダードナンバーのメロディだ。
会話はすべて途絶え、大石の弾くピアノの旋律だけが、紫煙の渦巻くホールを支配していた。
Red roses for a blue lady
――あの方に赤いバラを。
I want some red roses for a blue lady
男でも背負いきれない重責に、たったひとりで耐えているあの方に。
座興の演奏でありながら、大石は生真面目な表情でピアノに向かっていた……。
「オオイシ提督は音楽の才もあったのか?!」
驚いたようにマッキントッシュ大将が磯貝に囁きかけた。
「は、私も初めて耳にします……」
誰もが思いもかけない大石の姿だった。
マッキントッシュは茫然と彼を見つめていた。
なんの遅滞もつかえもなく、鍵盤の上を滑る大石の十指。
均整のとれた半身、撫でつけられた黒い髪、真摯な、でもどこか物憂げな横顔。
自分でも癪なことに、マッキントッシュは胸の内に大石への賛美が沸き起こるのを止められなかった。
最後のメロディが余韻を残して消えていった。
万雷の拍手と歓声に大石はにっこりとほほ笑むと立ち上がった。
※ ※ ※
『兵学校に入るまでずっと外人教師が教えに来ていた。うちはそういうハイカラなことが好きな家でな』
帰りの機内で磯貝がそっとピアノの事を聞くと、大石は照れくさそうにそう答えたという。
「ふうん……。長官はそういやブルジョアだったな」
磯貝の報告に、原は遠くを見るような眼をした。
「聴きたかったな、俺も……」
「また弾いて下さいませんかね」
「そうだなぁ。残念ながら軍艦にピアノなんて無理だから、たぶん……」
――戦争が終わってからかな。
ふたりは少しさびしげに微笑みかわした。
「いつかまた、機会があればいいですね」
「うん」
「それでは私はこれで失礼いたします。おやすみなさい」
「ああ、ご苦労だった、おやすみ」
磯貝は深夜の右舷通路にそっと出て行った。
ひとりになった室内で原はぼんやりと大石のピアノに思いを巡らす。
どんな曲なんだろうな。レコードがあれば聴いてみたいが。
ノートの余白に彼は備忘のために書きつけた――Red roses for a blue lady と。