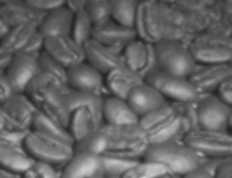
長官室には芳醇なコーヒーの香りが漂っていた。
大石秘蔵のブルーマウンテンだ。
出所はもちろん英女王陛下ご本人である。
大石は真珠の粒を扱うような丁寧さでコーヒー豆をよりだしていた。
彼が趣味だと言い切るコーヒーの抽出作業が始まる。
この日も客である原の存在を忘れたかのように、大石はコーヒー豆をミルで挽きドリップする一連の作業に熱中しだした。
原も話しかけたりして大石の楽しみを邪魔するつもりはない。
コーヒーの香りの中で、うきうきとした表情をして慎重に手順を踏む大石を原は温かく見守っていた。
(ふふ、いつ見てもじつに楽しそうな顔をなさるなあ)
大石のコーヒーはたしかに美味い。
しかし原にとっては大石が見せる楽しげな表情のほうが貴重だった。
大石とふたりきりでコーヒーの香りに包まれてすごす静かなひとときは、原にとって掛け替えのない時間であった。
大石は薫り高い黒い液体を丁寧にカップに注いだ。
原は大石の満足そうな横顔に心が和む。
「さあ、今日も出来は上々だ」
満面の笑みとともに大石はコーヒーカップを原の前に置いた。
(さあ、言うぞ……)
「女王陛下のコーヒーだ。味わって飲んでくれ」
(ふふふ……)
大石の決まり文句に原は頬のほころぶ。
「はっ、有難く頂戴します」
礼を言ってカップを受け取った原の鼻先を、柔らかなブルーマウンテンの湯気がくすぐる。
(いい香りだ)
熱い液体を原は一口啜った。
(……美味い)
向かいで大石もカップを口元に運んでいた。
目を伏せてコーヒーを味わう大石の表情に、ふと原は違和感を覚えた。
いつもの自分の作品を賞味する満ち足りた表情ではない。
逢えない人に思いを馳せるような、そんな甘い感傷的な表情の翳りを原の鋭い目は見逃さなかった。
(この前もそうだった……原因はこのブルーマウンテンか……)
大石に関しては原は自分の直感に自信があった。
(まさかとは思うが、女王陛下……?)
原も英女王を敬愛するにやぶさかではないが、大石の場合はそれだけでないような気がする。
もしそうなら……。
原はそこまでで考えるのをやめた。
大石の心の奥にまで踏み込むつもりはない。
彼のほうから心の奥を見せてくれるのでもないかぎり。
ともあれ大石はこうして原だけには惜しまず秘蔵のブルーマウンテンを振舞ってくれるのだから……。