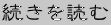◆幕僚選び 〜続き
ほう、これは……!
大石は掘り出し物のウェッジウッドを値踏みするような目つきでその男を見た。
賑やかな座敷の中で、その男は終始寡黙で深沈とした表情のまま、まずそうに杯の酒を舐めている。
男にしては長い睫毛がときおりゆっくりまばたきしていた。
……なるほど、軍務局の原大佐か。
日中戦争勃発前、高野が海軍次官だったときに、海軍大臣秘書官だったのが当時少佐の原である。
大臣秘書官をはじめ軍務局局員、海軍省副官と、赤レンガとよばれる海軍省の中枢で長らく勤めてきた経歴の持ち主らしく、原はひとめで切れ者とわかる風貌をしていた。
……軍務局課長なら実務能力は折り紙つきってことだな。
原の見るからに鋭敏で理知的な横顔は、いかにも帝国海軍の内外の政策プロパーを担当してきた人物らしい。
経歴からすると彼は完全に軍政系の軍人である。
常識的に考えれば、艦隊参謀長には戦術作戦に携わってきた軍令系の俊才がふさわしい。
だが作戦はすべて自分で立案してしまうつもりの大石には、作戦のプロである軍令部出身の参謀長などかえって邪魔な存在になりかねない。
万一その秀才が頭の固い人物だったら、万事自己流の大石とことごとく対立してしまうだろう。
……作戦は俺が立てる。俺の参謀長は細かい帳尻合わせをする世話女房でいい。
そんなことを胸のうちでふてぶてしく呟いてみせる大石である。
高野があえて軍令部出身者を推薦しなかったのは、そんな大石の性格をよく飲み込んでいたからに違いない。
さすがは高野総長、そのあたりの読みは深いといえる。
一通り観察を終えた大石はずかずかと広間を横切り、原の前にまっすぐに進んだ。
「俺は大石だ、軍務局の原君だな?」
そう声を掛けて、大石はどっかと原の正面に腰を据えた。
不審げに目を上げた原に大石は笑いかけて
「まあ、一杯」
と膳部の銚子を取り上げた。
「は……頂戴します」
居住まいを正した原が硬い声音で答えた。
大石蔵良……一緒に仕事をしたことはなかったが、原も顔と評判ぐらいは知っている。
海軍四天王のうちのひとりに数えられながらも、最近はポストらしいポストにも就かず「予備役五分前」ではないかと取りざたされていた将官だ。
それが今年度の進級発令でしっかり中将に昇進したのは、どうやら対独戦用に設立される新艦隊の司令長官に大石が内定しているらしいと海軍省内で囁かれていたのも原は耳にしていた。
その大石がなぜ自分のところまでわざわざ来て構うのか、原にはさっぱりわからなかった。
大石によって満たされた盃を、原はゆっくりと口許に運んだ。
少しだけ盃の酒を口に含むと、彼はやや苦そうな顔つきで嚥下した。
そんな原の動作を大石が目を光らせて注視していた。
切れ者だと噂は聞いていたが、大石は本人を間近に見るのはこれがはじめてだった。
軍務局の原大佐……M軍務局長の懐刀。
端麗な容姿にもまして、彼の澄んだ目の色がことのほか大石の気に入った。
毅然としてクールに構えながらも、その瞳は真っ直ぐな光を失っていない。
仕事熱心で任務以外に心を動かされない一途な男の瞳だ。
何かを企むかのような表情で、じっと自分を見つめる大石の視線に気がついて、原はいぶかしそうに杯から目を上げた。
そんな原に瞳を当てたまま、ニッと大石が片頬だけで笑いかけてきた。
「君はフランス語に堪能だそうだな」
「駐在経験がありますので日常会話でしたらなんとか」
「いいことだ! どうだ、ひとつまた欧州に行ってみたくないか?」
「……それはどういうお話でしょうか」
「いや、これは唐突すぎたな、すまん、ウフフ……」
何がおかしいのか、大石は原の目をしっかりと見つめたまま愉快そうにひとりでほくそえんでいる。
初対面だというのにずいぶんと馴れた態度だったが、原は不思議と嫌な感じを受けなかった。
大石が笑うと口のはたに深い片えくぼがきゅッと寄る。
態度はやや尊大だし言葉つきもどちらかといえば横柄だが、彼の人なつこいえくぼがそんな欠点を押し流してしまう。
不躾に自分を見つめる大石の視線も、そのえくぼのせいで温かな好意的なものに感じられて、原は不快に思わなかった。
にぎやかな酒宴の片隅で交わされた、大石の無遠慮な興味深げなまなざしと、原の静かな澄んだまなざし。
互いに強い印象を受けて、ふたりはしばし無言で向かい合った。
「おい大石! こっちでもっと飲まんか!」
「わかった、今いく」
とうに酔いが回っている同期に背を叩かれ、大石はあっさりと原の前から腰を上げた。
「近いうちに一度、ゆっくり話そう」
そう声だけ残して自分の席に戻っていく大石の後ろ背に、原は軽く頭を下げた。
……欲しいな、あの男。
杯を受け、飲み干し、機嫌よく歓談しながらも、ときおり大石の目は離れた席の原に注がれていた。
……ぜひ、欲しい。だが軍務局長があっさり手放すかな?
大石は杯を含みながら、原課長を援英艦隊の参謀長に貰い受けるべく、その交渉手段をあれこれと思案していた。
にぎやかな酒席に浮かれることもなく、ひとり静かな原。
そんな彼の姿を目の端に捉えながら、大石はふとほくそえむと右手の指で耳たぶをつまんだ。
……なぁに、いくらでも手はある……こういうことは搦め手からが常道さ。
酒盃を手にした大石の目が意地悪くきらきら光っていた。
まったく悪巧みに関しては大石の頭脳は天下一品である。
数週間後、何がどうなったのかもわからないうちに、M軍務局長は彼の自慢の部下をまんまと援英艦隊に引き抜かれてしまっていた……。