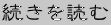◆絵はがき
内地からの郵便物が届いた日は、夕食後の頃合いの時間を見計らって、原が磯貝の部屋をのぞきにくる。
磯貝ももう慣れていて、参謀長の訪問の目的も呑み込んでいた。
「いらっしゃい。今月は《蝶々殺人事件》の後編ですが、お読みになりますか?」
磯貝はにこにことベッドの上に積まれた郵便物の山から、姉からの慰問品を引っ張り出した。
彼の姉は推理小説好きな弟のために、いつも数か月分の雑誌の切抜きをまとめて綴じて送ってくれている。
「ん……。《獄門島》の続きはないのか?」
わざと興味のなさそうな顔つきで、原はぼそっとつぶやいてみせる。
「ええ《獄門島》は先月休載だったそうです」
残念そうな色を隠しきれない原に、磯貝は笑いをかみ殺しながら雑誌の束を手渡した。
悪趣味だの低俗だの、いつもさんざん貶してはいるが、原が送られてくる推理小説を楽しみにしていることは、とうに心得ている。
だからこそ磯貝もまず原に続きを読んでもらうことにしている。
「いつも、すまん」
渋々のように原は視線をそらして礼を言うと《蝶々殺人事件》を受け取った。
「……またたくさん、はがきが来ているな」
きまり悪げにつぶやくと、原はベッドの上の郵便物に目をやった。
「よろしければご覧になっててください。私は失礼して返信を書いてしまいますね」
「ああ、俺なら構わんでくれ」
気軽な調子でうなずくと、原は磯貝のベッドに腰を下ろした。
原は磯貝の部屋に遊びに来ると、来客用の硬い椅子には掛けず磯貝のベッドに腰掛けるのを常としていた。
長居するときは、ベッドに行儀悪く寝そべることも珍しくない。
きっちりとした原参謀長も磯貝の部屋に来ると気を許してリラックスするらしい。
このごろは大して遠慮もせずに、磯貝の私物をかき回したりして結構長い時間遊んでいく。
磯貝はにっこり笑って椅子に戻ると、また机に向かい便箋にペンを走らせだした。
原が磯貝に来たはがきを見たがるのも、いつものことだ。
彼に言わせると、磯貝に来るはがきは量も多いしバラエティに富んでいて、なにより本人に合わせて能天気な内容ばかりだから、読んでいて飽きないそうだ。
磯貝もまた、私信を見られても一向に嫌そうな顔をしない。
べつに見られて困るような手紙や艶っぽい手紙はない。
原は磯貝があらかじめそういった郵便物は取り分けて隠しているのかと思っていたが、ほんとうに来ていないらしい。
無言で原は磯貝に来たはがきに目を通していた。
同期生、故郷の友人、揃いも揃って手紙好きらしい磯貝の親族たち……。
いろんな年代、多様な職業の人がいる。
鮮やかな手跡もあればひどい癖字もあり、可愛い子供の絵手紙さえある。
このはがきたちが書かれた内地の茶の間に原は思いを馳せる。
遠く離れた日本の暮らしや風物の温もりが、磯貝のはがきから濃く暖かく伝わってくる……。
やがてごろん、と原は腰掛けていた磯貝のベッドに背を倒した。
寝転がったまま、原は一枚の絵はがきを手にしてぼんやりとその自筆らしき水彩画に見入っていた。
達者な筆遣いで、庭のケイトウが描かれている。
原の実家の庭にも、晩夏になると毎年緋色のケイトウが頭を並べていたものだ。
(もう何年目にしてないだろう……)
毎年わざわざ蒔かずとも、こぼれ種から立派に育った塀際のケイトウ……。
絵はがきをひっくり返して、表書きの通信文も彼は読んだ。
原の薄く開いた口許から、白い歯がちらりとのぞいた。
書き添えられた文がユーモラスだったのだろう。
差出人は磯貝の中学のときの恩師らしかった。
「ああ、宮島じゃないか」
原は思わず懐かしそうな声を上げた。
「宮島に親戚でもいるのか?」
原は一枚の絵はがきを手にして半身を起こすと、机で手紙の返事を書いている磯貝に声を掛けた。
「いいえ、それは紅葉谷の茶店のおばさんですよ」
「なんだそれは」
原は笑って私信に目を走らせた。
――今年ノ弥山登山ハ生憎ノ雨デアリマシタ、泥ダラケニナッテ生徒サンタチハ元気ニ隊列ヲ組ンデ歩カレマシタ――年配の婦人らしい、やや震えた筆跡が宮島での懐かしい兵学校行事を伝えてきていた。
どういう縁で磯貝がこの宮島在住の婦人と文通するようになったのか……気の優しい磯貝のことだ、何かの事でお礼状を出して、また返信が来て、賀状を出して、と何年も小さな縁を大切にしてやり取りを続けているに違いない。
机に向かってせっせと返信を書いている、この無類に筆まめな男を、原は不思議そうな顔で眺めた。
そして手にした絵はがきの『錦秋の宮島』にもう一度目をやる……。