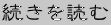◆続・冬の怪談〜続き
「そうか」
事情を飲み込んだ大石は鋭い目を閉じるとくすりと笑った。
(まったく、おまえたちときたら。そんなことだろうと思っていたが)
大石は安堵したのか悪戯っぽく原の目を見た。
「なあ原君。まるで小学生だぞ。好きな女の子をいじめるガキ大将だ」
原がむっとして何か言いかけた。
それを大石は遮って話し続ける。
「まあ怒るな、ものの喩えだ。……うーん、この場合適当な喩えじゃなかったな……妹をいじめる兄貴と言ったほうがいいか。なあ、原君、君には妹はいるか?」
「……いえ、おりません」
大石のピント外れな喩えに閉口して原は低い声で答えた。
「そうか。俺も兄貴だけで女兄弟はおらんのだ」
大石は気にせずそんな原に微笑んで見せた。
「以前は磯貝を弟だと思えとおっしゃったのに、今度は妹ですか?」
原はばかばかしくなってフッと笑った。
「ふふ、やっと笑ったな」
嬉しそうに大石は原の両肩を掴んで彼の目に笑いかける。
「なあ、つまらん事を気にするんじゃない。それよか、磯貝のことを気にしてやれ。かわいそうじゃないか」
原はためいきをついた。
……結局は磯貝のことなのか。
……あいつは簡単に人の同情を集めてしまう。俺は同情なんかごめんだと突っぱねてしまう。その辺が可愛げがないんだろうな、俺という人間は。
原はうら悲しい気持ちになりながら、漠然と考えていた。
……長官もまず磯貝に同情するんだな。
鈍い心の痛みが原を密かに苦しめた。
「嫌いでいじめているんじゃないんだろう?」
大石は原の気も知らず、言葉を続ける。
嫌い……なのか、どうなのか。
原は自分でもわからなかった。
……あんな素直に生きていけたらどれほど人生は楽になるだろう。
軽い羨望を原は磯貝に感じた。
原は自分にそそがれる大石の眼差しを感じながら、静かに磯貝のことを思った。
あいつは馬鹿だけど、自分に正直なやつだ。
肩肘張らずに自然にそのままの自分で生きている。
俺には出来ん。
結局は羨ましいんだろうか。
なんかあいつだけには好き放題言ってきたな、俺は。
あいつは人の言葉をそのまま素直に受け取るから、こっちもストレートにものが言える。
心の裏を探りあう必要もない。
たしかに一緒に話していて、子供のときに帰ったような気分になる。
けんかしても、あいつは次の日にはけろっとしているような、そんな気がして。
懐いてくるあいつの愛情をいいことに、俺はついつい我儘に振舞ってしまう。
それどころか、俺はときどき無性にあいつを思いっきり踏み付けにしてやりたくなる……。
あいつが憎いのか好きなのか、俺は自分でもわからない。
一方、大石もそんな原をじっと見守っていた。
……原が今までいろいろと我慢してやってたことは俺がよくよく知っている。
磯貝も見違えるほどいい参謀になったじゃないか。
原の手柄だ。
よく辛抱してやった。
原の整理能力と磯貝の折衝能力。
俺にはどちらも貴重な戦力だ。
頼むから仲良くやってくれ。
いや、おまえたちの場合、喧嘩にもなっていない。
子供のじゃれ合いだ。
……俺はおまえたちをまとめて抱きしめてやりたい気分だよ。
「ご心配をかけました。磯貝には謝っておきます」
「そうしてくれるか」
大石はほっとしたように笑顔になった。
「それに、もう公室に籠るのはやめにしてくれるんだな? そばにいてくれんとどうもその、寂しくていかん」
照れたような顔で大石は目を逸らして言った。
「いえ、仕事が溜まっているのは本当なんです」
「そうか……。あまり根を詰めるんじゃないぞ。息抜きにコーヒーぐらいは付き合ってくれ」
「ありがとうございます」
原は軽く頭を下げた。
原の長いまつげが彼の頬に影を落としている。
寂しげなその表情に大石はふと胸騒ぎを感じた。
「どうした? なんだか元気がないようだが」
原は目を上げて安心させるように微笑んで見せる。
大石が自分を心配してくれているのはわかる。
(でも俺を特別に思って……というわけではない。わかっていたつもりなのに)
大石にそんな期待をかける自分を原は心の中で憐れんだ。