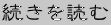◆続ひげ(前編)
磯貝は私室で鏡を覗き込んでいた。
こんなに熱心に鏡を見るのは、ニキビだらけだった十代以来かもしれない。
四角いごつい顔にきょとんとした二重の大きな目、たしかにニキビの頃とあまり変わらない童顔だ。
ブ男とまでは思いたくないがハンサムには程遠い……そう彼も思っている。
(……そりゃ、小さい頃は正久は金太郎さんみたいで可愛いと親兄弟は言ってくれたが)
それ以来、人に可愛いなんて云われたのは今日が初めてだ。
(ん? どうした赤くなって。可愛いやつだな……)
大石の囁き声が耳元に甦った。
きゃん、というような奇声をあげると磯貝は手鏡を手にしたままベッドに身を投げた。
「……」
嬉しいような、くすぐったいような。
なんといっても大石長官は彼の憧れの人である。
しばらくそのまま彼はベッドに伏せていたが、起き直ると今度は鏡に向かって大口を開けた。
まだチクチクする喉を見てみようというのだが、そんな喉の奥まで見えるわけがない。
磯貝は諦めて手鏡を置いた。
(……俺、何してたんだっけ?)
机の上にはさっき医務室で貰ってきた軟膏が置いてあった。
(ああ、切り傷に薬を塗ろうとしていたんだ)
磯貝はもう一度手鏡を手に取ると、ひげを剃ったときの傷に軟膏を塗りつけた。
机には専門誌が数日前から積まれたままになっている。
参謀たるもの、海外の戦術論文にもきちんと目を通しておかなければならない。
磯貝は専門誌を手にとって気の乗らない様子でページをめくった。
細かい英字がびっしりと並んでいる。
磯貝はしばらく嫌そうな顔で何ページか読んでいたが、うんざりしたのか十分もしないうちに本を閉じてしまった。
(だめだ、今夜も勉強する気になれない)
磯貝は専門誌を机の上に戻すと、両手を頭の後ろに組んでため息をついた。
(なんだかさぼり癖がついてしまったなぁ)
そう思いながら無意識にあごに手をやった。
磯貝の角ばったあごはつるんとしていた。
一週間、ちくちく、ざらざらしてくるひげに手をやっては気にしていたことを思うと、さっぱりしたような寂しいような妙な心持ちである。
机の前に座ったものの磯貝は手持ち無沙汰だった。
勉強はしたくないが、さしあたり他にすることもない。
(そうだ、読むものがあった!)
磯貝の目が輝いた。
先日届いた慰問袋の中に雑誌の連載小説の切り取りがあった。
戦術論文を読んでから読もうと引き出しの中にしまっておいた、あれである。
切り取りはきれいに鋏で切り揃えられ、仕付け糸で丁寧に綴じられていた。
こういう心遣いをしてくれるのは彼の姉である。
推理小説の好きな弟に評判のいい連載小説をこうしてまとめては送ってくれるのだ。
『堂々の新連載!! 横溝正史 本陣殺人事件』
手に取った雑誌の荒い手触りと印刷インクのツンとした匂いに磯貝はわくわくした。
……磯貝はすぐに横溝の世界に引き込まれていった。
ドアがノックされた。
三本指の男の死体を発見したばかりの磯貝は、ノックの音に飛び上がった。
「磯貝! 寝ているのか?」
ドアの外で誰かが呼んでいる。
「はっ! どうぞ!」
磯貝の返事にドアを開けて顔をのぞかせたのは原だった。
「参謀長……」
珍しい客に磯貝は目をぱちくりさせて椅子から立ち上がった。
「おまえが私室に持ち帰ったと聞いたんでな」
原は戦術論文の載っている専門誌の名を出した。
「あ、私です。あの、参謀長もまだお読みでなかったのですか?」
「まだだ」
(いつもおまえのフォローに大忙しで本も読めやしない。わかってるのか?)
腹の中でむかっ腹をプチッと押しつぶすと原はぶっきらぼうに答えた。
「読む暇がなくてな。今日はようやく時間ができたから読もうと思って参謀室へ行ったら、おまえが持ち帰ったというから」
「それはすみませんでした……」
磯貝が頭を下げる。
「あれか?」
原の素早い目が磯貝の机の上に積まれた専門誌に留まった。
「もらっていくぞ」
つかつかと原は机に近づき専門誌を取り上げた。
「もうおまえは読んだんだな?」
「いえ、じつはまだ……」
「なに? まだだって?」
原の目が陰険に光り、磯貝の机に広げられている雑誌に向けられた。
「で、おまえは今これを読んでいたんだな? なんだこれは? 日本の雑誌の切り抜きか」
ぱっと原の手が手製の綴じ本をさらって表題を確かめた。
「宝石? ……娯楽雑誌だな。本陣殺人事件? なんだこれは?」
怠学の現場を押さえられてしまっては、磯貝も言い訳の仕様がない。
「横溝正史の最新作でありまして、推理小説です」
「探偵小説か。横溝?」
「おもしろいですよ、ぜひ一度お読みください。こっちはもう読みましたから」
磯貝は既読分の綴じ本を原に持たせて、代わりに大事な読みかけの綴じ本を取り返した。
彼にしては機敏な行動である。
「あ、うん……。時間があれば読んでみよう」
めずらしく磯貝がこんなに熱心に勧めてくれるものを、押し返すのはいくらなんでも気が悪い。
それに長く日本を離れていると日本の本が懐かしくなるものだ。
原はおとなしく綴じ本を受け取った。
「肝心の論文をそっちのけにして読むぐらいだから、さぞおもしろいんだろうな」
にっと笑って原は部屋を出て行った。
「じゃ、これも借りていくぞ」
ドアがバタンと閉まり、磯貝は部屋にひとりになった。
まずい状況にもかかわらず、原に怒られずにすんで彼は胸を撫で下ろしていた。
原が彼に向ける「仕方のないやつ」という視線はあいかわらずだが、以前に比べるとその温度はかなり温かくなっていた。
原のほうで大きく譲歩して彼の存在を受け入れようと努力してくれている。
磯貝も何とかそんな原の努力に報いたかった。
できることなら何でもして原のために働きたかった。
いまはまだ足を引っ張るほうが多かったが……。