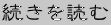◆アイスランド料理〜続き
冬のアイスランドの昼は短い。
昼前になってようやく朝日が昇ったと思えば、午後三時には日が沈む。
雲の厚い日などはそのわずかな昼間でさえ、うす暗いままだ。
しかしそんな頼りない太陽といえども、日没前と日没後では冷え込み方が違う。
除雪されただだっ広い道路に立って、早水たち四人は足元から這い上がる寒気に身震いした。
小さな町に駐留軍を当て込んだ飲食店やダンスホールが立ち並んでいる。
旭日艦隊が来る前から米軍がドルをばら撒いていたので、至極景気はよさそうだ。
彼らの横を酔っ払った米兵の一団が通り過ぎて、一軒の店の中に消えた。
「アメリカさんのドルはなんと言っても強いですからな」
米兵を見送って木島が肩をすくめた。
「派手にドルをばら撒くから、この辺の物価が上がったなんて話もあるぐらいで。実際スカパフローより物が高い」
「この町で財布を気にせず食えるのは魚だけだな」
「ちゅうか、魚料理しかないけどな、わはは」
原と磯貝は顔を見合わせた。
食べ物がうまいと言って誘っておきながら、ずいぶんな言い草ではないか。
一行は一軒の店に入った。
ドアの中はムッとするほど暖かい。
豊富な温泉を利用したスチーム暖房が全島に普及しだしている。
少し硫黄臭がするのが難点だが、慣れてしまえばなんということもない。
暖かい湯気と煙草の煙。
ここも米軍人で繁盛している。
料理が高いせいか客層はいずれも将校ばかりだ。
木島たちは平服だが、彼らは軍服のまま遊びに来ているので階級は見ればわかる。
金髪の女の子があちこちのテーブルで彼らの相手をしている。
英語の談笑と女の子たちの嬌声がにぎやかだった。
どうもただの料理店にしては女の子が多すぎる。
(ふん、やっぱり)
じろりと原が木島と早水を睨んだ。
いそいそと出迎えた女主人が一行を席に案内した。
おそらく木島と早水は上得意なのだろう。
金髪碧眼の北欧美人が中年になるととたんにズンと貫禄と横幅をつけるのは、ここアイスランドでも同じようだ。
彼女は一行の中で一番体格のいい磯貝よりも背丈も横幅もひとまわり大きかった。
『いい日に来た。今日はいいロブスターが入っている』
彼女は片言の英語で愛想よく勧めてくる。
「じゃ、それを。それと焼き魚を食べたいんだが」
早水が磯貝を見て笑いかけながら注文する。
『サーモンはどうだろう?』
「いいね。それから子羊のシチューと、ええと、ドライフィッシュの……」
『ハルズフィスクール?』
「それそれ。デザートはスキールで」
『わかった。飲み物は?』
「ここの特製のを頼むよ」
『わかった』
女主人が大きく頷いて厨房の方に去った。
「なんだ、特製のって?」
原が早水に聞きただした。
「自家製の焼酎です。結構フルーティーでいけますよ」
「ふうーん。まあ酒はあんたたちでやってくれ。俺と磯貝は承知のとおり下戸だからな」
「はっ。しかし話の種に一口だけでもどうぞ。アイスランドの芋焼酎なんて他所じゃ飲めませんや」
「芋焼酎?」
原は怪訝な顔をした。
まさか最果ての北の国でそんなものに出会おうとは。
やがてテーブルいっぱいに皿が並べられた。
ロブスターが無造作に積み重ねてある。
サーモンの横には大きなホタテも添えられていた。
そして真っ黒な細長い魚の燻製。
「うわあ……」
磯貝が珍しいご馳走に目を輝かす。
「……なるほどこれは豪勢だな」
原は早水が皿に取り分けてくれたロブスターのひげをフォークでつついた。
原がフォークを取ったのに合わせて、大佐三人もナイフフォークを取って食事を始める。
たしかに材料は新鮮でうまい。
魚介類はもちろん、羊肉も臭みがなくて柔らかい。
(しかし、どうも塩っ辛いだけで、味付けに芸がないな)
だがまあ、こんなものかな、と原は思う。
イギリスでも、あまり美味いと思う料理に出会ったことがない。
日本武尊のコックのつくるフランス料理のほうがうんと美味い。
(ま、磯貝が喜んで食べているんだ。よかったんじゃないか)
向かいの席で五尾めのロブスターと格闘している磯貝に目をやって、原は口角をかすかに上げて微笑んだ。
皿の上の魚介が消え、ロブスターの残骸だけがうずたかく積まれている。
まったく磯貝はよく食う。
少食な原と早水の倍は食べただろう。
皿が下げられ、女主人がデザートを運んできた。
「ああ、そうだ。磯貝さん、パンケーキでしたね」
早水が磯貝に聞いてやると、彼は嬉しそうにこくんと頷いた。
「パンケーキはできるかね?」
『できる』
「参謀長はいかがですか?」
「……俺はもういい」
原がげんなりした顔で答えた。
デザートも要らないくらいだ。
「じゃ、一人前だけ。木苺をたっぷりかけて、あちらに」
早水は期待に目を輝かしている磯貝を指して注文した。
『わかった、まかしておけ』
女主人は磯貝に愛想良く頷くと、厨房に消えた。
「……なんだかオーナー、今日はえらくサービスに来るなあ?」
不思議そうに早水が首を傾げる。
「いつもは女の子に任せきりなんですがね?」
「磯貝さんの食べっぷりが気に入ったんじゃないか?」
「はは、かもしれん。若いとはいえ食欲旺盛だねぇ、磯貝さん」
「いや、めずらしい料理だったんで、つい。……あ、これも変わってますね」
磯貝は小さなグラスの中のプティング状のどろりとしたデザートを口に運んだ。
「あれ? ヨーグルトですか?」
「甘くて、くどいな」
磯貝と原が一口食べて変な顔をした。
「スキールというアイスランド特有の乳製品ですよ。……なんでも精がつくそうで、ぶふふ」
「……はぁ」
ニターッと笑ってみせる木島を磯貝は不気味そうに見た。
「よく食えるな、おまえは」
呆れたように原が呟く。
(どういう胃袋をしているんだ? それも見ただけで胸がやけそうそうなものを……)
「……甘くてうまいです」
真っ赤な木苺シロップをたっぷり吸い込んだパンケーキを、磯貝は幸せそうに頬張る。
磯貝以外は焼酎をオンザロックで飲んでいた。
原は一口飲んでグラスを置いてしまった。
ジャガイモとキャラウェイの実が原料のかなり強い酒だ。
木島と早水はグラスを片手にそれとなく女の子を物色している。
(ふふん、そろそろ本性を現すか?)
皮肉な目つきで原はふたりを見ていた。